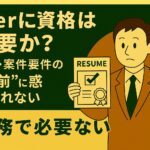「SI業界のお金事情」現場目線で読み解く収入のリアル
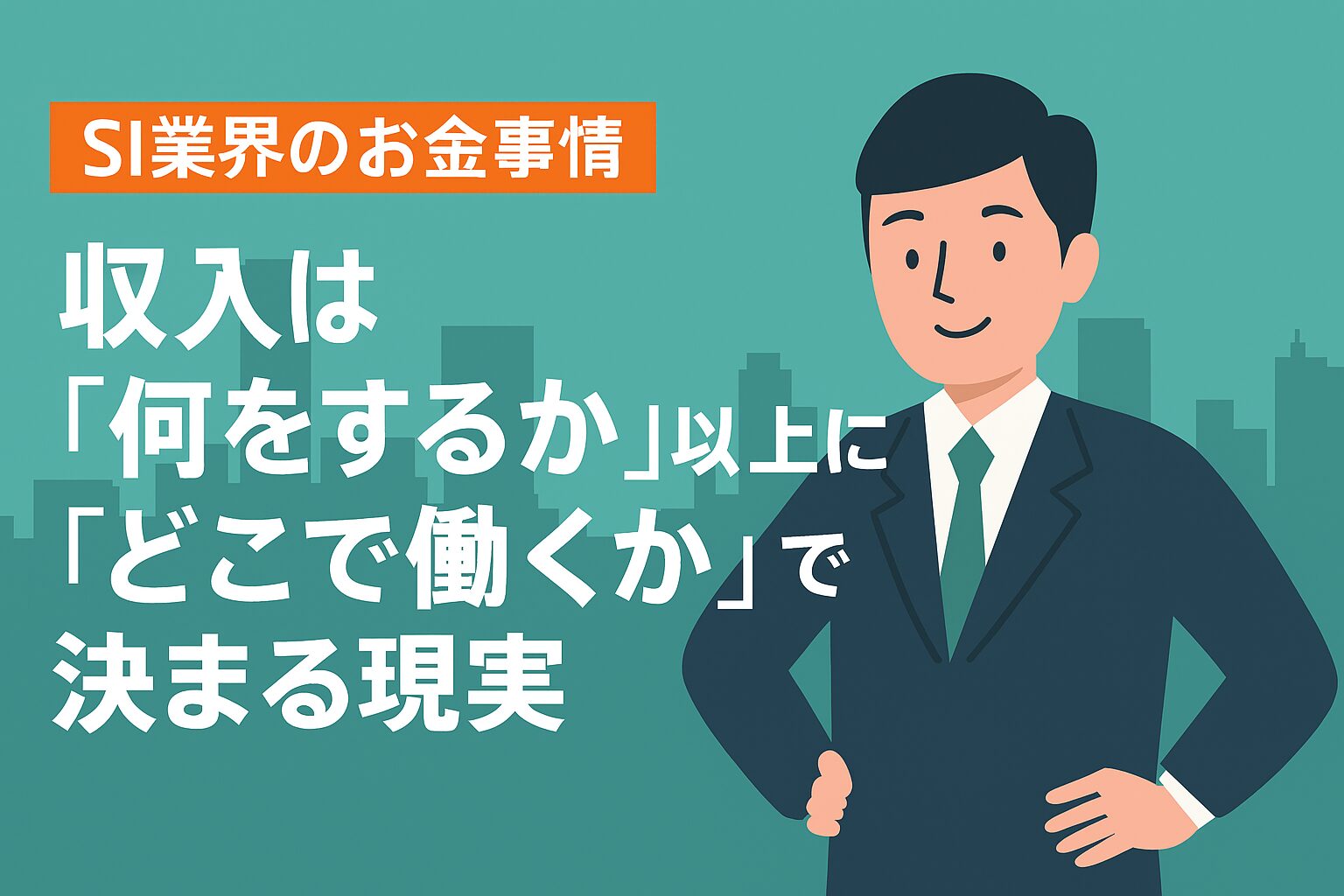
目次
はじめに:SIerの収入は“実力”より“ポジション”で決まる
SI業界で働いていると、「自分よりスキルが低い人の方が給料が高い」と感じることがあります。 それは決して気のせいではありません。SI業界では、「何をするか」より「どこで働くか」が収入を大きく左右します。
本記事では、SI業界の収入構造を“ポジション別”に分解し、昇進・独立・フリーランスなどの選択肢を現場目線で読み解いていきます。
昇進・昇給の現実:サラリーマンの限界
多くのSIerは「昇進すれば給料が上がる」と思っていますが、現実は厳しいものです。
-
- 昇給は年数%が基本。年収500万→550万に5年かかることも
- 昇進すれば責任は増えるが、報酬は微増
- 部長・課長クラス以上は“一握り”。失敗すれば降格・左遷もあり
- 「上に行けば収入が増える」は幻想になりつつある
昇進は「収入を上げる手段」ではなく、「責任を増やす制度」になっている企業も少なくありません。
役員・社長の収入:夢はあるが現実は厳しい
「社長になれば年収1,000万以上」と思われがちですが、実態は企業規模によって大きく異なります。
- 中小企業の役員・社長は年収800万〜1,200万程度が一般的
- 大企業なら年収数千万〜億も可能。ただし「仕事ができる」だけでは無理
- 世渡り力・政治力・社内人脈が不可欠。技術力だけでは届かない領域
つまり、社長や役員は「実力+運+人脈+社内政治」が揃って初めて到達できるポジションです。
独立の世界:収入は“自分次第”、ただしSIとは別の能力が必要
独立すれば収入は青天井になりますが、同時に安定性はゼロになります。
- コネクション・営業力・契約力がすべて。技術力だけでは仕事は来ない
- SIerとしてのスキルは「実務力」であり、「事業力」ではない
- 独立=別ゲーム。準備と覚悟が必要
「自分で稼ぐ力」がなければ、独立しても収入はむしろ下がる可能性があります。
ポジション別の取り分構造:ユーザ企業 vs プライム vs 下請け
SI業界では、契約構造によって収入の取り分が大きく変わります。
📊 図解:SI業界のポジション別取り分構造
| ポジション | 取り分 | 備考 |
|---|---|---|
| ユーザ企業(発注者) | 100% | 予算を持つ側。最も強い |
| プライム(1次受け) | 60〜80% | 顧客と直接契約。利益率が高い |
| 2次受け | 30〜50% | 中間マージンあり |
| 3次受け以降 | 10〜30% | 実務者だが取り分は最小 |
- 下に行けば行くほど、同じ仕事でも取り分が減る
- 「どこで働くか」が収入を左右する最大要因
この構造を知らずに働いていると、「なぜ給料が上がらないのか」が永遠に分からないままになります。
フリーランスという選択肢:同じ仕事で収入1.5倍も可能
フリーランスになると、マージンが少ない分、報酬がダイレクトに反映されます。
- 例:正社員で月40万 → フリーランスで月60万(同じ業務内容)
- 経費は移動費程度。ほぼ手取りに近い
- 税金・保険は自己管理。残しておく意識が必要
- 契約延長されるだけで、収入は安定する
SI業界のフリーランスは「準委任契約」が多く、成果物ではなく“稼働”に対して報酬が発生するため、他業界のフリーランスより安定性が高いのも特徴です。
まとめ:収入を上げるには“場所”と“立場”を見直すこと
- スキルアップだけでは限界がある
- 昇進・独立・フリーランスなど、収入構造を理解した上で選択することが重要
- 「自分の仕事が、どこで・誰に・いくらで売られているか」を知ることが、収入改善の第一歩