プロジェクト成功の秘訣は“目的理解”と“認識齟齬の防止”にある
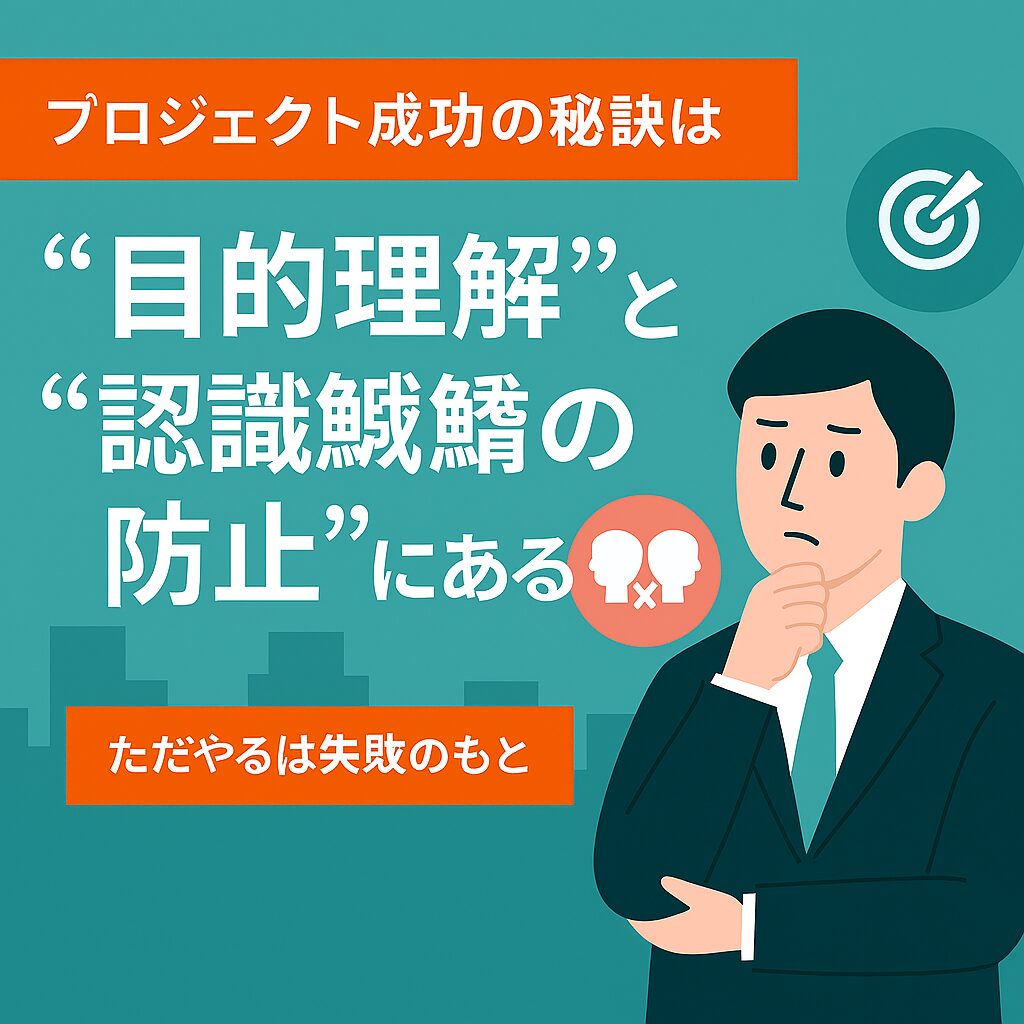
目次
はじめに:PJ失敗の原因は「ズレ」から始まる
SI業界でよくあるのが、「仕様通りに作ったのに、ユーザから不満が出る」という現象。 これは、技術力や作業精度の問題ではなく、認識のズレ=認識齟齬が原因です。
そしてこの齟齬は、作業の進め方や設計の順序を誤ることで、誰にでも起こり得ます。 本記事では、PJ成功のために必要な「目的理解」と「齟齬防止のステップ設計」について、現場目線で解説します。
※補足:プロジェクトが成功すれば、あなた自身の評価も上がりやすくなります。 成果物だけでなく、プロセスの質が評価に直結するのがSI業界です。
目先の作業を“なんとなく”やると、なぜ失敗するのか
「とりあえず振られた作業をやっておく」 「画面仕様が来たから、設計に入る」 このような進め方は、PJ失敗の第一歩です。
なぜなら、その作業が何の目的で必要なのかを理解していないから。 背景が見えないまま進めると、ユーザの期待とズレた成果物ができあがります。
タスクの目的・背景を理解することの重要性
目的を理解することで、以下のような判断が可能になります:
- 仕様に抜け漏れがあるかどうか
- 設計方針が目的に合っているか
- ユーザの期待に沿った提案ができるか
背景を知らずに作業すると、ユーザの「本当に欲しいもの」からズレてしまいます。 目的理解は、設計・実装・レビューすべての精度を高める“土台”です。
認識齟齬が起きるメカニズムと防ぎ方(ステップ設計)
認識齟齬は、以下のような要因で発生します:
- 粒度の違い(画面単位 vs 業務単位)
- 言葉の定義のズレ(「登録」と「保存」など)
- 前提の不一致(業務ルールや例外処理)
これを防ぐには、以下の順序で構造化することが重要です:
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 目的 | なぜこのPJが存在するのか(業務課題・KPI) |
| ② 方針 | どういう方向性で解決するか(業務改善/システム化) |
| ③ ユースケース | 実際の利用シーン(誰が・いつ・何をする) |
| ④ 業務フロー | 業務の流れとシステムの関与 |
| ⑤ データモデル設計 | 業務と画面を支える構造。テーブル設計・関係性・命名の整合性 |
| ⑥ 画面・機能 | 実装対象の具体的な粒度(UI・API・処理単位など) |
この順序を踏むだけで、ユーザとの認識齟齬はほぼ防げます。 特に⑤のデータモデル設計は、業務とUIの橋渡しとして極めて重要です。ここがズレると、後工程がすべて破綻します。
ユーザ不満 vs 納得 vs 満足:PJ成功の3段階
PJの成果は、ユーザの反応によって以下の3段階に分かれます:
| 段階 | 内容 | 成果 |
|---|---|---|
| ユーザ不満 | 欲しいものからズレている | 「なんか違う」「使いづらい」 |
| ユーザ納得 | 依頼通りに作る | 「ちゃんとやってくれた」 |
| ユーザ満足 | 背景まで理解し、気づいていない課題も解決 | 「頼んでよかった」/再依頼・紹介につながる |
多くのPJは「納得」で終わりますが、満足に到達できると、信頼・継続・評価が一気に高まります。 そのためには、ユーザ自身が言語化できていない課題まで拾う必要があります。
まとめ:目的→方針→構造→作業の順で進めるべき理由
PJ成功は「作業の正確さ」ではなく「認識の一致」で決まります。 目先の作業に飛びつかず、まずは“目的”から逆算すること。
この構造を理解すれば、PJの成功率は大きく変わります。 そしてPJが成功すれば、あなた自身の評価・単価・キャリアにも直結します。






