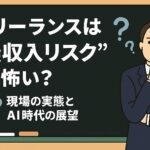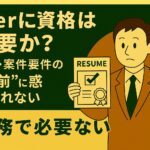フリーランスの“損害賠償リスク”は本当に危険?契約・実務・相手選びで守る方法
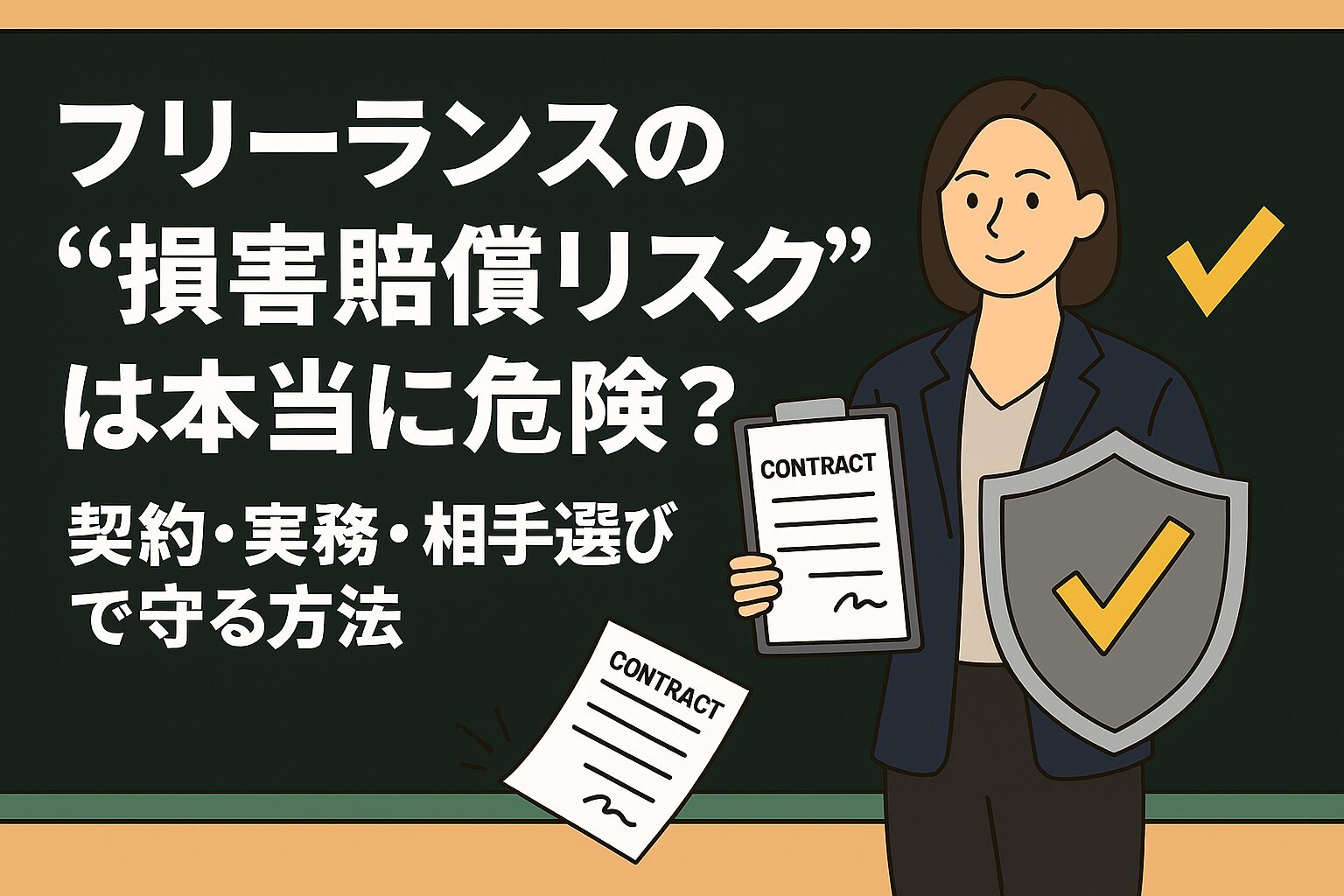
目次
はじめに:フリーランス=自己責任というイメージ
フリーランスになると、「何かあったら全部自分の責任」という不安がつきまといます。 特に損害賠償リスクは、契約書に「損害が発生した場合は…」と書かれているだけで、怖く感じる人も多いでしょう。
しかし実態は、サラリーマンと大差ありません。 契約・実務・相手選びの3つを押さえれば、損害賠償リスクは十分にコントロール可能です。
実際のリスク:何が損害賠償につながるのか?
損害賠償と聞くと「何かやらかしたら数百万円請求されるのでは…」と不安になりますが、現場で起きるリスクは以下のようなものです。
| リスク項目 | 内容 | 実態 |
|---|---|---|
| 貸与物の破損・紛失 | PCやスマホなど | サラリーマンでも同様の責任がある |
| データ流出・削除 | 誤操作・管理ミス | 注意すれば防げる。多くはヒューマンエラー |
| 業務遅延・納期不履行 | 納期遅れによる損失 | 事前報告・調整で回避可能 |
| 機密保持違反 | 情報漏洩・SNS投稿など | 契約違反になるが、常識的な行動で防げる |
つまり、“普通に仕事をしていればまず起きない”リスクがほとんどです。
契約で守る:損害賠償の上限と責任範囲を明記する
契約書でリスクを限定することは、フリーランスにとって最も重要な防御手段です。
✅ 必ず入れてもらうべき文言
- 「損害賠償は報酬額を上限とする」 → 万が一のときでも、請求額が青天井にならないようにする
- 「乙の責めに帰する場合を除く」 → 自然災害や相手側のミスまで責任を負わされないようにする
この2つが入っていない契約は、リスクが不明瞭で危険です。
🔍 契約時に確認すべきポイント
- 上限額の明記(報酬相当)
- 損害の定義(直接損害か、間接損害か)
- 責任の範囲(第三者への影響は含むか)
- 契約書のテンプレートが整備されているか
実務で守る:日々の習慣が最大の防御
契約が整っていても、実務での習慣がなければ意味がありません。 “事故を起こさない”よりも、“起きたときに説明できる”状態を作ることが重要です。
| 実務習慣 | 内容 |
|---|---|
| 貸与物管理 | 紛失防止、持ち出し制限、物理ロック |
| データ管理 | バックアップ、アクセス権管理、誤操作防止 |
| ログ・履歴 | 作業記録、変更履歴、証跡の確保 |
| 事前報告 | 問題発生時の即報、納期調整の相談 |
これらはすべて「サラリーマンでもやるべきこと」であり、フリーランスだから特別というわけではありません。
相手選びで守る:変なベンダーと契約しない
損害賠償リスクは、契約相手がまともかどうかで大きく変わります。
- プライムベンダーであれば、法令順守・フリーランス尊重の文化があることが多い
- 一方で、契約管理が甘いベンダーや、下請け構造の末端では注意が必要です
- 変なベンダーと契約すると、いちゃもんをつけられるリスクがある
🔍 契約前に品定めすべきポイント
- 契約書の整備状況(テンプレートの有無、交渉余地)
- 担当者の対応(説明責任・透明性)
- フリーランスへの扱い(報酬支払・業務範囲・責任分担)
- 口コミや過去事例(SNS・知人経由)
フリーランス側も「契約される側」ではなく、契約する側として相手を選ぶ視点が必要です。
まとめ:損害賠償リスクは“契約・習慣・相手選び”でコントロールできる
- フリーランスだからといって、過剰にリスクを恐れる必要はありません
- サラリーマンでも同様の責任はあります
- 契約で上限と責任範囲を明記し、実務で習慣化し、相手を見極めれば 損害賠償リスクは“管理可能なもの”になります